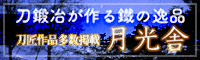- Home
- 連載エッセイ「刀のかたち・人のかたち」
連載エッセイ「刀のかたち・人のかたち」
第3回「下駄屋」
僕が小学六年まで、祖父が履物を営んでいた。屋号は「不二屋」。終戦後すぐに始めた。どこかに弟子入りして下駄職人になったのだが、詳細はわからない。戦前、金沢で生活していたから、その時に技術を習得したのかもしれない。
大鋸屑だらけの作業部屋は、祖父の聖域だった。桐などの材料が、天井まで積まれてあった。壁には、刃先が大小の鑿や丸い部分を削る弓のような道具が張り付いていた。それを外から見ると、どれ程に祖父が道具を丁寧に扱っているのかうかがい知れた。柄の部分はその使う人の握り具合のカタチに変形していた。長年の結果だ。窓からの光が、その刃たちに当たり、天井は幻想的な輝きで踊った。
祖父の一日は、道具の手入れから始まる。午前六時に起き、砥石に向かう。その姿は沈黙の人だ。自分が納得いくまで作業に、季節を無関心のままに、祖父の手は荒れていた。ごつい、無骨な皮膚には、砥ぎ汁が吸い込み、黒い筋が残っていた。洗っても落ちない。
「こいつらが下駄の良し悪しを教えてくれる。それに応えるのが俺の仕事だ」
寡黙な職人は、商売が下手だった。父は後をつがなかった。店の赤字を父の給料が補った。そのために、お客がいても、親子喧嘩の声が響いた。時代は、下駄を履く習慣から遠のいていった。それでも、桐など材料を購入する。職人が、職人でなくなる悲哀を知っていたのだ。
数年後、祖父に痴呆症状が出始めた。道具を扱うのを危惧した父は、突然の廃業を祖父に宣告した。同業者に残った材料や道具を一夜にして売さばいた。唖然と祖父はそれを眺めていた。人は張りを失うと、花のように落下するようだ。一年後、祖父の葬儀が行われた。やせ細った体に似つかわしくない大きな手が記憶に残った。