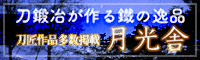- Home
- 連載エッセイ「刀のかたち・人のかたち」
連載エッセイ「刀のかたち・人のかたち」
第1回「父の小刀」
八年前、父が亡くなった。末期癌であることを家族は告げなかった。八十キロ近い体重が半分になれば、それに気がつかないはずはない。だが、父は「検査入院」のまま、黄泉へと去った。
葬儀が終わり、僕は自室で深酒した。涙が涸れ、溜息とも咳きともつかぬ、肺臓から溢れた。頭の中は、どんよりした雲が立ち込めていた。父との思い出を探ろうとしても、何も浮かばない。毎日のように、病室を見舞ったのに、ろくざま会話をしていない。冷めた父子だったのか。
酔ったためか、引き出しを抜いてしまった。無造作に落ちたものを拾う。その中に、錆びた小刀を見つけた。どうしてここにあるのか思い出せない。それは、父が、小学三年の僕に買ったくれたものだ。
「鉛筆は、こうやって削るのだ」
父の自慢げな声がした。真新しい小刀は、恐ろしいほどよく切れた。父は新聞紙を広げて鉛筆を削る。微かに木の匂いがする。僕はその様子を凝視した。芯の先が、針先のように尖っていた。父の命令に従い、それを見本に僕は鉛筆を削る。だが、父のようには削れない。僕の手に添えて、父は小刀を使った。父の体臭が背中に流れた。それは、快い匂いだった。
「小刀を使えないと友だちに笑われるぞ」父の声が耳底から噴いてきた。小刀を見失って四十年以上が過ぎた。翌日、僕は砥石でそれを磨いた。表面は、鈍い輝きを持った。しかし、父の小刀はあの時の輝きではない。
僕は子どもに小刀を与えなかった親だった。父の思いも伝えられなかった。小刀を使えることが一人前と見られた父の時代は、昔話なのか。人間の叡智から生まれた刀剣が「悪者」扱いされている。どこか、僕たちは大切な文化を失いかけている。