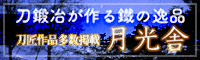- Home
- 現代日本刀の歩み ― 戦後篇 ―
現代日本刀の歩み ― 戦後篇 ―
第1篇 「現代刀」の定義についての再検討
栗原彦三郎の意図したもの
前者が、「日本刀の廃絶は日本精神の廃滅につながる」と考え、「刀匠精神の涵養(かんよう)と鍛刀技術の上達」を設立目的に掲げたのに対して、後者は「国粋たる日本刀を鍛錬し、主として将校、同相当官の軍刀整備に資する」と、文言を異にしている。結果から見れば、いずれも時代の思潮を反映しつつ、組織的に作刀の復興を企図したこと、本格鍛錬を墨守したこと、多くの刀匠を養成したことなど、共通点は多い。しかし、両者の違いを端的に言うなら、軍刀の製作を目指したか否か、である。この設立意図の相違には、大きな意味がある。
栗原彦三郎も軍刀と無縁ではなかった、との異論もあろう。確かに無縁ではなかった。昭和12年に日中戦争が勃発すると、直ちに軍刀修理団を組織して自ら大陸に赴いている。それは同14年まで十数次にわたった。自作を軍刀として提供してもいる。だが、栗原はある時期まで、軍刀の製作を否定していた。
初期に師範を務めた笠間一貫斎繁継との伝習所運営をめぐる対立と袂別(べいべつ)は、まさに軍刀を介した作刀観の違いに根本の原因があった。軍刀の需要に応えて製作するなら、伝習生の訓練にも伝習所の維持にも寄与すると笠間が主張したのに対して、栗原は断固これを退けた、との証言がある(両人に師事した山上昭久)。
頭山満(とうやまみつる 安政2年<1855>~昭和19年)は昭和10年4月、東京・渋谷の自邸内に常磐松(ときわまつ)刀剣研究所を開設し、笠間を迎え入れるが、この裏には、笠間との確執によって栗原が傷つき、日本刀の復興が挫折することを危惧する頭山の配慮があったものとみている。頭山と栗原との関係は、それほど深く、三十余年の永きにわたった。
栗原にとっての日本刀は「日本精神の象徴」であり、「国家鎮護の霊器」であった。切れ味を重視はするが、単なる武器ではない。これに携わる刀匠にも技術以上のものが求められる。「日本刀の復興」とは、古来の伝統とそのふさわしい担い手を現代に蘇らせることにほかならなかった。帝展第4部への出品の実現(昭和9年)、大日本刀匠協会の結成と新作日本刀大共進会の開催(同10年)、文部省後援による新作日本刀展覧会の開催(同10~18年)などは、そのような真意に基づくものである。
にもかかわらず、栗原をして「軍刀報国」の流れに身を投じさせたのは、国家の危急という歴史の大きなうねりであった。しかし、全国の刀匠に軍刀増産を呼びかけても、最後まで粗製を容認することはなかった。求められて揮毫(きごう)する際も、あえて「鍛刀報国」「以刀剣報国家」と言葉を選んだように思われる。