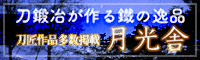- Home
- 連載エッセイ「刀のかたち・人のかたち」
連載エッセイ「刀のかたち・人のかたち」
第5回「刀という道具」
「時代劇」と言えば、必ず刀で斬りあうシーンがある。勧善懲悪のシナリオが作られ、我々日本人の心情に訴えかける。「悪者は殺されてしかるべき」との考え方が優先して、斬られる側は一般的に悪者になる。テレビの影響力は凄い。簡単に、視聴者にも悪者はどちらなのか判る。
僕が、子どもだった頃には、「赤堂鈴之助」とか「鞍馬天狗」が流行った。「チャンバラ」 をするのが男らしい遊びだった。斬られ役は誰もやりたくはない。斬る側の主人公は、くじ引きで決めた。
チャンパラに嫌気がさしたのは、小学生六年頃だ。「人殺し」に、正義があるのかと疑問に思ったのだ。大人への発想が芽を葺き始めた。「切捨て御免」という、封建社会の身分制度を学んだとき、憤りを感じた。僕が悪者でなくとも、いつでも斬られる側になる可能性があるからだ。
それに、裁判にかけられる前に殺されては、「私刑」と変わらない。米国の「西部劇」にもいえる。インディアンが次々殺されるシーンが楽しいのか。冷静にならなくとも、斬られる=殺されるとのイメージが定着した。
どうしてか、斬る道具としての「刀」が、使い人間と同じ扱いを受けるようになった。道具は決して自ら作動するものではない。これまで、ものの見方や考え方を簡単に訓練された僕たちは、すぐに悪者探しをしたがる。「親が憎けりゃ、子も憎い」との諺のように、刀を使う者が恐ろしければ、刀も恐ろしいとの考え方が一方通行する。
迷惑なのは、刀自身であり、刀を作る刀工たちだ。何も人殺しのために、この世に登場したのではない。鉄を鍛え、その最高峰の道具としての刀を生み出した。誤ったのは、使う人間自身ではないか。大人と子どもの差異がそこにあるのではないか。